2025/08/22

最近、建築現場で「建築許可第〇〇号・・・施主ロロ」等と書いた看板を見かけるようになりました。これは、その建築が行政による認可を受けたものであることを知らせるものなのでしょうが、私はこの「施主」という語の使い方に少々首を傾げざるをえません。
もっとも、最近の辞典で「施主」の項を見ると、説明の三番目くらいに「建築・設計などの注文主」と出ていますから、そんな意味での使い方も公認されてきたのかもしれません。しかし、本来の「施主」は<布施を行なう恵みの主>、すなわち仏教上の善行をして、<僧侶や困っている人々に供養する人>を指すことを忘れてはなりません。始めに挙げたような用例は、本来の「施主」を、<財物を出して供養する当事者>として狭く取り、それが転じて一般に依頼者や注文主を指すようになってきたのだと思われます。
それにしても インド語のダーナ(旦那・檀那・檀越と音写する)の意訳である「施主」が、建築用語になろうとは……。言葉は斯くも変わるものかと感心せざるをえません。 一方、「旦那」という語も、いまではかなり違う意味で用いられておりますね。奥さんが夫を旦那と呼んだり、商売のお客さんを旦那と言ったり、あるいはお金持ちを旦那と持ち上げたり……。しかし、いずれも元は「施す人」としてそう呼んだことが推定できるでしょう。そう呼んでくれる相手に金品を施さない若旦那は、まさにバカ旦那です。また、菩提寺のことを檀那寺(旦那寺)ということがあります。この場合は、お寺から施してもらえるものは「仏の教え」ということになります。檀那である寺は檀越たる家、すなわち檀家に法の布施をし、檀家はお寺や僧侶に財の布施をする。ちょうど交換するような形ですが、これを財法二施と言って、その功徳は無量とされています。ぜひ本来の布施をなし、本物の旦那・施主になりたいものです。
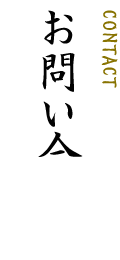
お問い合わせやご質問等についてはこちらよりお願いいたします。
また、毎月の鬼子母神講(毎月8日 午後7時)や七面さま講(毎月18時 午後2時~)へのご参加も
心よりお待ちしております。
日蓮宗 妙栄山 法典寺
〒418-0023 静岡県富士宮市山本371-1
Tel.0544-66-8800
Fax.0544-66-8550